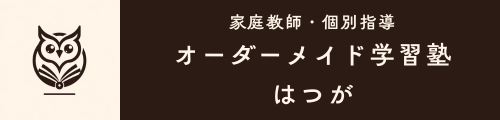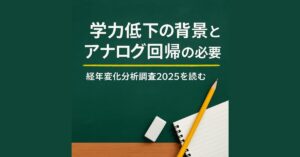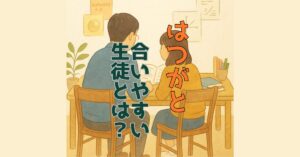漢字を書かない中学生 ― 背景とアナログ回帰の必要性
こんにちは、オーダーメイド学習塾はつがのちだです。今回は漢字を書かない子どもが増えてきたことについてお伝えします。
はじめに ― 「漢字を書かない」現象との出会い
私は家庭教師や個別指導塾、中学校放課後学習支援などで多くの中学生と接してきましたが、ここ数年で特に印象的な変化があります。それは、「漢字を書かない」「漢字を覚えようとしない」生徒が目立ってきたことです。読めはするけれど書けない。文章を書いても、平仮名が多く、漢字の部分がすっぽり抜け落ちている。漢字テストになると、それなりの対策をしてくるが、いざ書くシーンとなれば、ひらがなやカタカナに寄っていくのが現実です。
背景① スマホ・タブレット文化の影響
最大の要因の一つは、スマートフォンやタブレットの普及です。予測変換や自動入力の機能によって、書くどころか「一文字一文字を思い出す」必要すらなくなりました。漢字は「覚えるもの」から「出てくるもの」へと意識が変化し、手を動かす機会は激減しています。こうして“書く筋肉”は日々使われず、記憶の定着力も低下していきます。学校の授業や連絡なども生徒所有のタブレットパソコンで実施するところが多くなりました。
背景② コロナ禍による学習習慣の変化
2020年の一斉休校から始まったコロナ禍では、多くの学校がオンライン授業に切り替わりました。その結果、黒板を写す時間は減り、画面を眺めるだけの受動的な学びが増えました。授業中に手を動かさない習慣は、漢字学習の基礎である「書き取り」の時間を奪いました。
背景③ 勉強時間の細切れ化と集中力の低下
スマホやゲーム、SNSが身近になったことで、勉強時間は細切れになりがちです。短時間で区切られる学習は集中力を奪い、「丁寧に書く」姿勢を持ちづらくします。結果として、覚えるべき漢字も頭に定着しにくくなります。
書くことの効果 ― 前頭前野の活性化
手書きには、単なる文字練習以上の意味があります。久しぶりに文字を書いてみたら、頭がガンガンした経験はありませんか。これは、文字を書くとき、脳の前頭前野が活性化し、思考や記憶、集中力が高まります。逆に、画面入力ばかりだと前頭前野の刺激は減り、学習全般の理解力に影響する可能性があります。「書くこと」が国語だけでなく、数学や理科、英語の学習にも波及効果を持つのはこのためです。性格面においても、粘ることが身に付きます。
現場での対策例
- 毎日5分の漢字手書き練習:短くても続けやすく、効果が積み上がる
- 授業ノートは必ず漢字で:平仮名書きを許さないルール化
- 小テストの活用:頻繁にアウトプットの機会を作る
- 紙媒体や本の読解:紙に書いてある文章をノートに写すことで、暗記ではなく理解ができる
特に「少しずつでも毎日」が大切です。まとめてやろうとすると定着しづらくなります。
保護者ができる家庭でのサポート
- 買い物メモを漢字で書かせる
- 手紙や日記を書かせる
- 覚えた漢字を家族でクイズ形式にする
- ゲームの種類も教養に近いものとする
勉強としてではなく、生活の中の自然な行為として書く時間を増やすのがポイントです。
まとめ ― デジタルとアナログのバランス
スマホやタブレットは便利で、これからも学習に欠かせないツールです。しかし、便利さに頼りすぎると、基礎的な「書く力」が衰えてしまいます。漢字力は国語だけでなく、他の教科の理解にもつながる土台です。デジタルを否定するつもりはございません。デジタルとアナログ、それぞれに役割があります。文字を書く事はアナログでも、何文字書いたかはデジタルを活用しても良いと思います。今こそ、デジタルとアナログのバランスを見直し、子どもたちに「書く習慣」を取り戻すことが必要だと感じます。
オーダーメイド学習塾はつが お問い合わせはお気軽に