― 親の思惑を手放すことから始める「信じる」という選択
「そろそろ変わってくれるはず」と思っていませんか?
不登校や登校しぶりの子どもと向き合う日々。
親として、「このままでいいのだろうか」「いつか戻れるのだろうか」という不安は当然のことです。
だからこそ、周囲から「信じて待ちましょう」と言われると――
「待っていれば、いつか元気になるはず」
「きっともうすぐ、何かが変わるはず」
と、どこかで**“良い変化を期待してしまう”**のが私たち大人の自然な心の動きです。
でも、もしその「待つ」が、“親としてこうなってほしい”という思惑の延長線上にあるなら……
それは、子どもにとっては「待たれている」のではなく、**“見張られている”**と感じられてしまうことがあるのです。
“何もしないこと”が「待つ」ではありません
「信じて待つ」と言われても、実際にはとても難しいものです。
- つい先回りして声をかけてしまう
- 励ましているつもりでプレッシャーを与えてしまう
- 何も変わらない日々に、焦りと苛立ちがつのってしまう
そんなとき、心の奥ではこんな思いが隠れていないでしょうか。
「いつになったら動いてくれるの?」
「このまま何もしないまま、ずっと続いてしまうのでは……」
それはつまり、“この子にこうなってほしい”という親の願いや思惑が、形を変えて表れているのかもしれません。
思惑を手放した「待つ」には、あたたかさがある
子どもは、親の言葉や態度から、思っている以上に敏感に気配を感じ取ります。
- 「変わってほしい」
- 「もう元気になって」
- 「みんなと同じように戻ってきて」
そんな願いが、**“愛情”という名のプレッシャー”**になってしまうこともあります。
本当の意味で「信じて待つ」とは――
親の思惑や期待をいったん脇に置いて
子ども自身が、自分の足で立ち上がるまでの時間を、安心して過ごせるようにすること
なのだと思います。
では、親には何ができるのか?
子どものペースを尊重しながら、今できること。
たとえば――
- 朝「おはよう」と声をかける(返事がなくても)
- 好きな食べ物を黙って用意しておく
- 部屋の灯りがついていたら、そっと「起きてるんだな」と気づく
そうした**「応答を求めない関わり方」**の中に、子どもが安心できる余白が生まれていきます。
信じるというのは、「選び続ける」こと
「信じている」と口で言うのは簡単です。
でも実際には、
- 望んだ通りの変化がない
- いつまで続くか先が見えない
- 周囲の声が気になって仕方がない
そんな中で、親が心穏やかでいられることのほうが少ないのが現実です。
それでも私たちは、
“この子は自分で乗り越える力を持っている”
“今はその途中にある”
と、選び直しながら、信じていく。
それが、「待つ」ということの本質ではないでしょうか。
最後に
待つことは、放任でも放棄でもありません。
「自分の願いや期待」をいったん手放し、
子どもが“今いる場所”に安心していられるよう支えること。
その関わりの中に、はじめて「信じて待つ」あたたかさが宿るのだと思います。
🕊 はつが ココロセーフティーサロンでは…
保護者のための対話と安心の時間を提供しています。
お子さまのことを考える前に、まずは親であるあなたの心が整うことが、何より大切だと私たちは考えています。
📌 初回相談・ご予約は
▶ ココロセーフティーサロン ご案内ページ
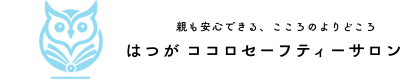
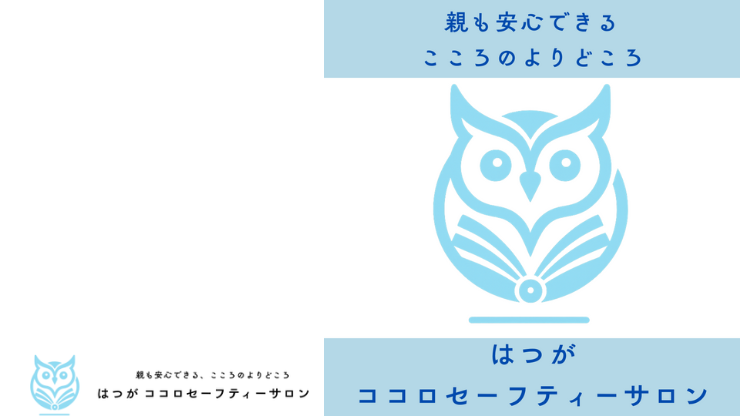

コメント