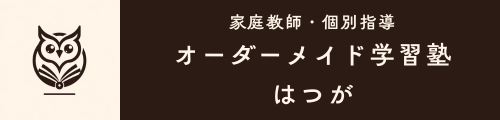親子の間に “風を通す” 学びのヒント 第2回 やる気がない? その裏にある “小さなSOS” の気づき方
こんにちは、オーダーメイド学習塾はつがの千田です。親子の間に “風を通す” 学びのヒント、今回は「やる気がない? その裏にある “小さなSOS” の気づき方」をお伝えします。
◇「やる気がない」ように見えるとき
「うちの子、全然やる気がなくて……」
そんな保護者の声をよく耳にします。けれど、実際に子ども本人と接してみると、「やる気がない」のではなく、「気持ちを出せない」「何かを抱えているだけ」だと感じることが少なくありません。
大人から見れば「やればできるのに」と思えることでも、子どもにとっては見えないプレッシャーや不安がブレーキになっている場合があります。
特に真面目な子ほど、心の中に“言えない小さなSOS”を抱えているものです。
◇実例①:先生の顔色ばかりうかがっていた男の子
中学1年生の男の子は、授業中ほとんど話さず、表情も固いままでした。問いかけても返事は小さく、言葉が続かない。そんな彼がある日、ポツリと「答えが間違っていたら怒られる気がして……」と漏らしました。
話を聞いていくと、小学校時代に先生から厳しく注意されることが多く、クラスでもからかわれた経験があるとのことでした。
私は彼に、「間違ってもいい。まずは言葉にしてみる、文にしてみることが大事」と伝えました。
間違っても怒られないとわかると、子どもは安心してアウトプットするようになります。わからないなりに話す・書くことができれば、その場で正しい表現に導くことができます。
「1回目の間違いはOK、2回目以降はNG」とルールを明確にすると、子どもも納得しやすく、安心感が増します。こうした積み重ねで彼も少しずつ言葉に自信を持てるようになり、やがて楽しそうに学ぶようになっていきました。
◇実例②:何も言わなくなった女子生徒の変化
中学2年生の女子生徒は、ある日を境に急に何も話さなくなりました。それまでは積極的だったのに、突然プリントに名前を書くのも嫌がるように。
理由は、友達からの何気ないひと言でした。
「それ、私にとって嫌なことだから」
この一言が彼女にとっては大きなダメージとなり、「どうせ私なんて……」と自分の殻に閉じこもってしまったのです。
私はマンツーマン指導の時間を活かして、彼女にこう問いかけました。
「もし誰もいなかったとしたら、自分はどんな人間だと思う?」
「変なことでも、おかしなことでもいい。自由に言ってみて」
すると、ぽつりぽつりとキーワードが出てきました。
「やさしい」「感謝の気持ち」「諦めない」「嫌なことを言われるとシュンとする」
「カメラ」「ファッション」「プレゼン」「IT」「アパレル」……
こうした言葉を手がかりに、彼女の“らしさ”を一緒に見つけていきました。
「ナンバーワンじゃなくて、あなたにしかないオンリーワンを目指そう」
と伝えると、彼女の表情が少し柔らかくなり、少しずつ笑顔が戻ってきました。
やがて彼女は、「他人の評価よりも、自分のできることを精一杯やる」と前向きな気持ちを言葉にできるようになったのです。
◇“やる気”よりも、“安心感”が先に必要
これまで多くの子どもたちと接してきて、私はこう確信しています。
やる気を引き出すより先に、「安心感」を届けることが大切だと。
子どもが心を閉ざしているとき、そこには「ここにいていいの?」「失敗しても怒られない?」という無意識の不安があります。
その不安を受け止めてくれる大人がそばにいることで、ようやく子どもは動き出すことができます。
心理的な安心があるからこそ、「考えること」「間違えること」が学びとして成立していくのです。
◇はつがの対応:ことばの“風通し”を整える
「オーダーメイド学習塾はつが」では、こうした子どもたちの小さなSOSに気づけるよう、次のような姿勢を大切にしています。
- 答えを聞くより、「どう考えたか」を尋ねる
- 表情・筆圧・沈黙など“非言語”のサインを丁寧に観察
- 結果よりも「その子のプロセス」に注目
- NG行動には理由を尋ね、理解したうえでルールを共有
- 他者と比べるのではなく、自分の中の「できた」に目を向ける
私たち指導者は、親でも学校の先生でもない「第三者」だからこそ、子どもとの間に“風通し”をつくる橋渡し役になれると考えています。
◇今日からできるミニ提案:「やる気がない」と思ったときの声かけ
子どもの様子がいつもと違うと感じたとき、ぜひこんなふうに声をかけてみてください。
- 「今日は何かあった? なんか、いつもと違う感じがしたよ」
- 「〇〇がイヤだったのかな? それとも、こっちの問題?」
子どもは、「気づいてくれてる」と感じるだけで心がゆるみます。
たとえ答えが返ってこなくても、“問いかけた事実”が信頼の土壌になっていくのです。
◇次回予告:「結果を出せ」の前に、“プロセスを見る力”を
子どもの学びを支えるうえで、「結果」よりも「プロセス」に目を向けることは、親や大人の“我慢力”が試される場面でもあります。
次回は、つい成果を急ぎがちな私たち大人の視点を見直すヒントをお届けします。