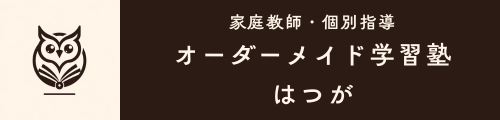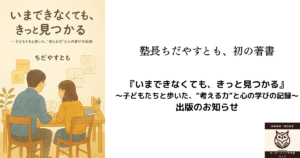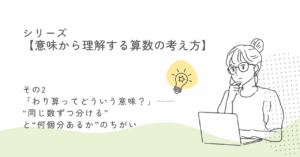シリーズ【意味から理解する算数の考え方】その1 九九が苦手でもだいじょうぶ──「かけ算って何?」から始めよう
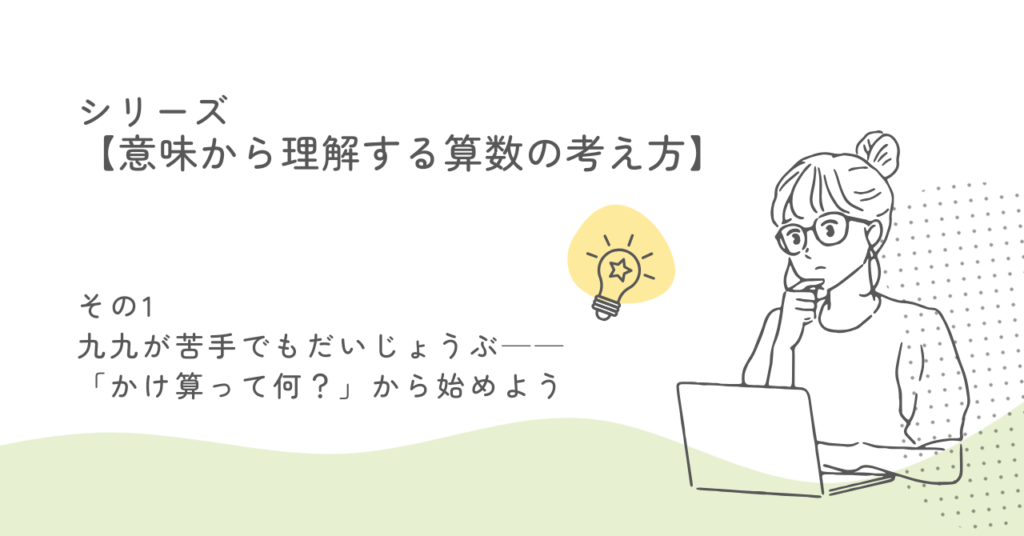
こんにちは、オーダーメイド学習塾はつが塾長の千田です。
「九九は覚えたはずなのに、割り算の文章題になると手が止まってしまうんです」
そんな声を、小学校2年生の保護者や、不登校のお子さんをもつご家庭からよく聞きます。
九九=暗記と考えがちですが、そのやり方が「わからないまま進むクセ」を生んでしまうこともあります。特に、九九の本質に触れないまま音だけで覚えると、割り算・文章題・図形との関連が見えにくくなってしまいます。
九九は「答え」だけじゃない。「考え方」を学ぶチャンス
九九が登場するのは、小学校2年生の2学期。
その多くが「リズムに合わせて覚える」「まずは1の段から言えるようにする」など、暗唱が中心の学習になります。
もちろん、リズムに乗って覚えるのは楽しいし、学習の導入としては有効です。ただし、「九九=歌のように覚えるもの」で終わってしまうと、「なぜそうなるのか」が置き去りにされてしまいます。
たとえば「2×3=6」は、「2が3こある」という意味です。
これは「2+2+2」と同じことであり、かけ算とは「同じ数のくり返し加算」であると理解できているかがとても大切です。
暗記だけの九九がもたらす“わからないの連鎖”
九九を音だけで覚えた子の多くが、次に苦手意識を持つのが「わり算」です。
「6÷2ってどう考えるの?」
「式を見て意味が分からない」
「答えは覚えてるけど、なぜその答えか説明できない」
このようなケースでは、かけ算の理解が浅かったこと、つまり暗記だけで分かったつもりになっている可能性が考えられます。
さらに、不登校のお子さんの場合、九九の暗唱をクラスみんなと一緒にできない、テンポよく言えないことで「自分だけ遅れている」と感じてしまい、ますます算数、そして学習から距離を取ってしまうケースもあります。
わかる→できるに変える「九九の教え方」
大切なのは、九九の「意味」をともに考えることです。
以下のような方法を取り入れると、子どもの理解がぐんと深まります。
✅ □×△=□が△こある
九九をただの音ではなく、「数の意味」に戻します。
「3×4」は「3が4こある」と言葉で置き換えるだけでも、理解が進みます。
✅ おはじき・マグネット・折り紙などの具体物で再現
3×4のときは、実際に「3個ずつのグループを4つ」作って見せてあげましょう。
逆に4×3なら、「4個ずつを3つ」です。この違いも、見て・触れて・並べることで自然に理解できます。
✅ 「何を何回くり返すのか?」を常に問う
「2×3って何?」と聞かれたときに、「2が3こだよ」と即答できるようになると、割り算にもスムーズにつながっていきます。
家庭でできる、今日からのサポート
💬 会話で「考え方」を引き出す
「3×4って何だと思う?」
「どうやってそれが12になるか、考えてみようか」
正解よりも、考える過程を一緒にたどる姿勢が何よりも大切です。
🛒 日常生活に九九を取り入れる
- スーパーで「同じお菓子を3こずつ4人分買うといくら?」
- おもちゃを「3こずつ並べて、何列で全部になるか考えてみよう」
など、日常にある“くり返し”を使って九九の意味を体験的に学べます。
暗記に頼らない学びで、自信と応用力を育てる
九九の意味がわかるようになると、次の学び(割り算、面積、文章題)にも自然につながります。
わからないまま先に進まず、理解できるところから積み上げることで、子どもたちの「自信」や「考える力」はぐんと育ちます。
特に不登校のお子さんには、学校でのスピードや形式にとらわれず、自分のペースで理解できる環境が重要です。
おわりに:九九が苦手でも、大丈夫
九九は「覚える」だけでなく、「意味を考えること」こそが、その後の算数を支える土台になります。言い換えれば、九九の暗唱が苦手でも、九九の考え方をしっかり理解していれば、スピードは関係ありません。
「九九が苦手かも」「すでにつまずいているかも」と感じたら、ぜひ一度立ち止まって、お子さんと一緒に考え直してみてください。
noteでも記事を書いています。ぜひこちらもどうぞ!
📚 オーダーメイド学習塾はつがでは、九九からやり直したいお子さん、割り算が苦手な中学生、不登校で学校のペースに合わないお子さんに合わせた個別の学びを提供しています。中央林間を中心に、町田・相模大野・大和駅周辺や東京都西部や神奈川県下の団地などで家庭教師スタイルと寺子屋スタイルを展開しています。お気軽にお問い合わせください。
→ 公式ホームページはこちら