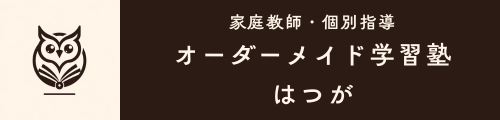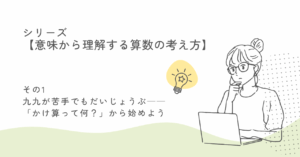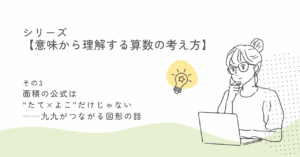シリーズ【意味から理解する算数の考え方】その2 「わり算ってどういう意味?」──“同じ数ずつ分ける”と“何個分あるか”のちがい
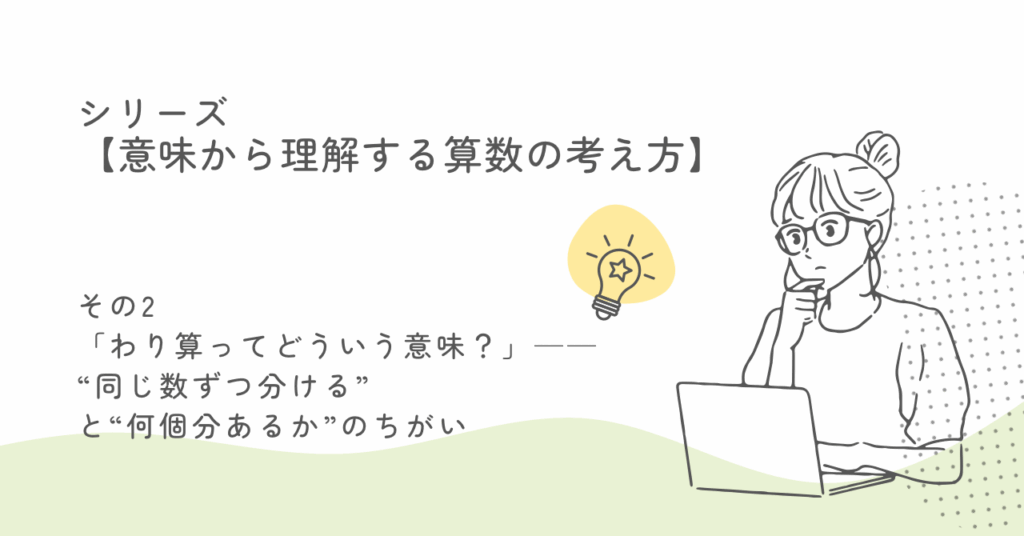
こんにちは、オーダーメイド学習塾はつが塾長の千田です。
小学3年生になると、いよいよ「わり算」が登場します。ところが、「なんだかよく分からない」という声をよく耳にします。
結局、九九を漠然と学んでしまうことで、わり算ができなくなってしまうようなのです。
「わり算って、ただの逆算でしょ?」
「同じ数を分けるだけだから簡単じゃない?」
と思うかもしれませんが、実は「わり算」には重要な意味が2つ隠れているんです。その違いを理解することが、後の算数や生活の中でも役立ちます。
わり算の基本的な意味
わり算は、算数の基本的な計算の1つですが、理解が進むと、単なる計算にとどまらず、さまざまな問題に応用できます。
まず、「わり算」とは、物を「分ける」ための計算ですが、その分け方には2つの視点があります。
1. “同じ数ずつ分ける”
これは、わり算でよく使われる考え方です。
例えば、「12個のお菓子を4人に分ける」という問題では、**「12を4で割る」と考えます。この場合、「12を4人に均等に分ける」**のが目的です。
式で表すと:
12 ÷ 4 = 3
つまり、4人のそれぞれが3個ずつお菓子をもらうということです。
2. “何個分あるか”
次に、「何個分あるか」という考え方があります。
「12個のお菓子を1人に4個ずつ渡すには、何人に渡せるか?」という問題です。この場合、**「12を4で割る」**と考えます。
式で表すと:
12 ÷ 4 = 3
この問題では、4個ずつ渡して3人に渡すことができます。
わり算の意味を理解するためのポイント
わり算を理解するためには、次のような方法を取り入れると有効です。
✅ 「分ける」ことに注目
わり算は、「同じ数ずつ分ける」と「何個分あるか」の2つの視点を意識して考えると、より深く理解できます。
✅ 具体物を使って視覚的に理解
おはじきやマグネット、折り紙を使って、実際に「12個を4人で分ける」とか、「12個を4個ずつ渡して何人に渡せるか?」を目で見て確認します。これにより、数式の背後にある意味が明確になります。
✅そして、何よりもかけ算を理解できていれば・・・・
かけ算は〇が何個という考え方です。2×3=6 は「2が3つあると6になる」。6÷3=2 は「6の中に3は何個ある?」と聞いている。つまり「かけ算とわり算はセット」なのです。
わり算を理解するための家庭でできるサポート
💬 日常生活でわり算を使おう
「お菓子を3個ずつ袋に入れたら、何袋できるか?」
「みんなでお昼ご飯を食べるとき、同じ量を分けるにはどうすればいい?」
家庭でも日常的に使われる「分ける」や「何個分」などの場面を考えて、わり算の意味を実生活に結びつけてみましょう。
🛒 数字に込められた意味を考えよう
「6 ÷ 2 = 3」など、数式が何を意味しているかを、声に出して一緒に考えてみることが大切です。「2個ずつ渡して、何人に渡せる?」など、数式を実際の場面に当てはめることで、わり算の本質が見えてきます。
最後に
わり算は、「同じ数ずつ分ける」と「何個分あるか」の2つの意味を意識することで、算数を楽しむための土台になります。どちらか一方の考えだけではなく、両方を使い分けることで、子どもたちの理解が深まります。
わり算が苦手な子どもたちは、「わかる」と「できる」をしっかり結びつけることが大切です。家庭でのサポートや、日常生活での実践を通して、「分ける」ことの楽しさを感じてもらえるような学び方をしていきましょう。
noteでも記事を書いています。ぜひこちらもどうぞ
📚 オーダーメイド学習塾はつがでは、九九からやり直したいお子さん、割り算が苦手な中学生、不登校で学校のペースに合わないお子さんに合わせた個別の学びを提供しています。中央林間を中心に、町田・相模大野・大和駅周辺や東京都西部や神奈川県下の団地などで家庭教師スタイルと寺子屋スタイルを展開しています。お気軽にお問い合わせください。
→ 公式ホームページはこちら